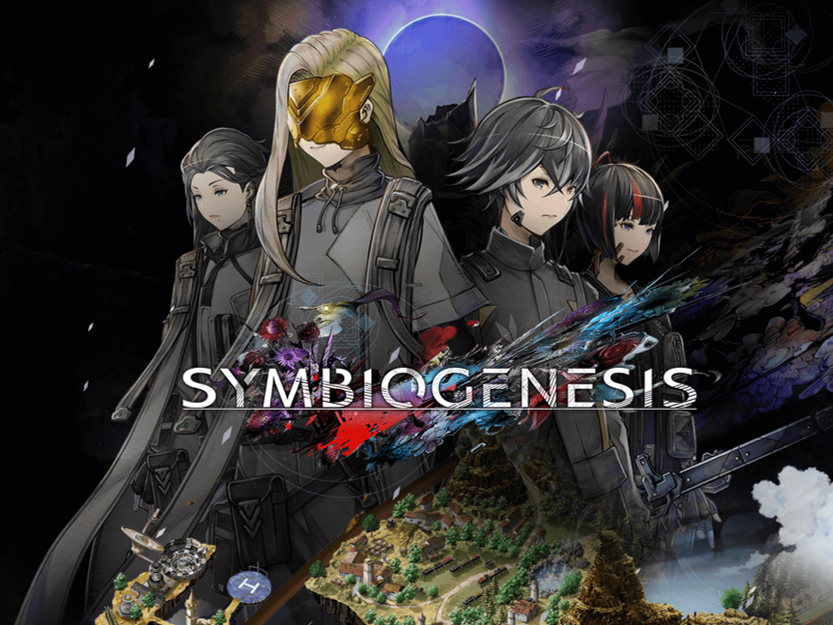
第二章からレプリカNFTの保有者にはメンバーランク経験値が加算されるようになり、レプリカNFTの価値が高まりました。プレイヤーはDiscordやXでレプリカ交換やGive awayを行い、レプリカNFTを集め始めましたね。
レプリカNFTを発行するには、「レプリカ発行ポイント(RP)」が必要です。RPはランクアップ報酬やNFTの購入者へのプレゼントとして配布されていました。しかし、第三章ではその仕様が大きく変化しています。落札枚数に応じた「レプリカ発行ポイント」のプレゼントはなくなり、ランクアップでもらえるRPも非常に少なくなってしまったのです。
ランク15で初めてRPが1ポイントもらえますが、その後はランク21までもらえません。「第3章から始めた人はレプリカ交換ができないのでは?」「第2章では分配プレイを、第3章では独占プレイをさせたい?」などの考えを投稿するユーザーもいます。
今回は「なぜ運営は、RP配布を制限しているのか?」に注目して、その理由を独自の視点で考察してみました。お時間の許す限りお付き合いください。
私は、運営がRP配布を制限する理由として6つの可能性を考えました。
1つずつ説明していきますね!
第二章ではRPが豊富に配布されていたため、レプリカNFTの大量発行が可能になりました。その結果として、マーケットにレプリカが溢れ、価値が下がった可能性があります。運営はゲーム内経済のバランスを取り戻すため、RPの供給を絞り、レプリカNFTの価値を高めようとしているのかもしれません。
RPの配布量が多すぎると、ゲームの進行や情報交換が簡単になりすぎ、ゲームのチャレンジ性や楽しさが減少する可能性があります。今シーズンは難易度を調整することで、プレイヤーが再び挑戦を感じられるゲーム体験を提供しようとしているのかもしれません。
RPの供給を絞ることで、プレイヤーは限られたリソースを効率的に使う必要があります。これにより、戦略的な行動や他のプレイヤーとの交渉が重要になり、ゲーム内でのコミュニケーションや協力プレイが促進される可能性があります。
プロデューサーの玉手さんやクリエイティブディレクターの豊田さんは、パプリックオークションで「情報交換という見えない流動性、コミュニケーションの楽しさ」を説明していましたね!
第三章のテーマや目標が、過去とは異なる方向性に設定されている可能性もありますね。例えば、レプリカNFTの量産よりも、オリジナルNFTの価値を再認識させるとか。他にも、新しい要素に注目させる意図があるのかもしれません。
もしRPが特定の課金要素やイベントで入手可能となるとしたら、運営が収益を上げるためにこの制限を設けた可能性もあると考えました。あるいは、新しいアイテムやシステムの導入を計画しており、それに向けた環境整備を行っている場合も考えられます。
RPの配布制限が、プレイヤーの行動を観察し、ゲームバランスのさらなる調整や新要素の導入に向けたデータ収集を目的としている可能性もあるでしょう。特に運営が「プレイヤーがどのように対応するか?」を知りたい場合、このような制限を実験的に導入することはアリだと思います。
運営の意図を完全に推測することは難しいですね。私の視点とは全く別の視点で、RPを絞っている可能性もあるでしょう。また、「経済バランスの調整」 や 「ゲームの戦略性向上」 などの単体ではなく、複合的な可能性もありますね。第三章が始まってまだ4週間ですので、私は今後の展開や運営からのアナウンスを待ってみようと思います。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。